Cybernetic being Visionとは、ムーンショット型研究開発事業 ムーンショット目標1「人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」の達成に向けた研究開発プロジェクト「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」の研究開発推進を担う研究者の思考に迫り、きたるべき未来のビジョンをみなさんと探求するコンテンツです。
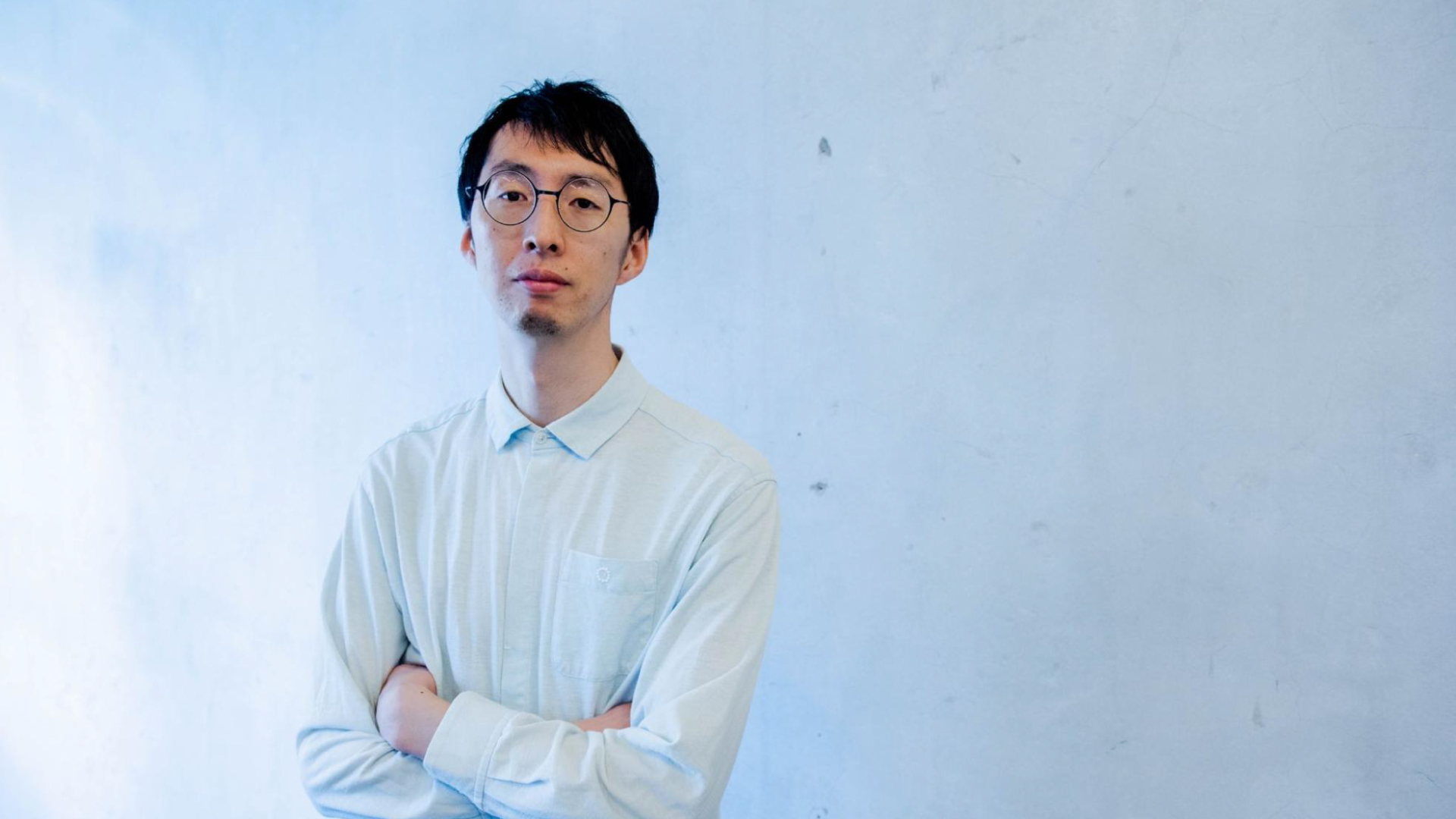
新山 龍馬
明治大学 理工学部 機械情報工学科・専任講師
ロボット研究者。2005年、東京大学工学部を卒業。2010年、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了、博士号取得。マサチューセッツ工科大学(MIT)にて研究員(コンピュータ科学・人工知能研究所、メディアラボ、機械工学科)を経て、2014年より現職。生物規範ロボットおよびソフトロボティクスの研究を主軸として、ディジタルとフィジカルを行き来できるロボティクスの開拓を目指す。著書に『やわらかいロボット』(金子書房)がある。
ウェブサイト:http://xrobotlab.jp/
認知拡張研究グループに所属する新山龍馬は、ロボット研究者だ。まさにサイバネティック・アバターの形そのものをつくりあげる役割を担うが、新山の創造性の根源は私たちがすぐに想像する「人型ロボット」や「メカっぽいロボット」などの既成概念を疑うことにある。人と共存するロボットは、日本人にとってはお馴染みの存在とも言えるが、同時に長らくアップデートされていない概念でもあるからだ。
まだ誰にも見えていない、次のロボティクス
昼下がりにソファでうたた寝をしていると、そっとブランケットをかけてくれる。
夕食に出かけようと準備をはじめると、スマートフォンを出して調べる前に近くのレストランの割引情報を教えてくれる。
翌日の仕事のスケジュールと、この先の仕事状況から身体にかかるストレスを割り出してくれ、運動不足を予測し、週終わりにエクササイズに行くことを勧めてくれる。
夕食から帰宅すると、家の掃除とベッドメイキングが済んでいて、ベッドの近くに部屋の湿度と体調から割り出された入眠時に必要な水がグラスに入っている。
そしてベッドのすぐ側で、すでに充電状態に入って眠っているのが私と共同生活をしている、アシスタントロボットだーー。
とても便利そうで、未来的で、話として聞く分には面白いなと思ってしまう新しいロボット像。しかし、こうしたロボットは現実のものにならないと私は考えています。
私はロボット研究者として、これまでさまざまなロボットをつくってきました。カエルのようにジャンプする「生物規範型ロボット」、人工筋肉などをつかったやわらかいロボット「ソフトロボティクス」などを研究してきました。
そのプロセスの中で感じたことは、世界中のロボット研究者にとって、次の「ロボティクス」はまだ見えていないということ、そしてロボットの世界観は少し前の時代の設定のまま止まっているということです。
世界に広く受け入れられているロボットのイメージは「オートメーション」に偏りがちです。それというのも、ロボット自体が1980年頃の産業用ロボットによるファクトリーオートメーションとして発展してきたものだからです。
冒頭のシナリオは、生活を自動的に豊かにするように書かれています。私たちはそうした、省人化・無人化を実現するものをロボットらしいと思い、無意識に便利なものだと感じてしまいます。
しかし、ロボティクスという概念は、そうしたロボットを生み出すためだけにあるものではないはずです。そして、既存のロボット像とは異なるものを着想していくことこそが、プロジェクト「サイバネティック・ビーイング」では求められていると感じて研究をしています。
ロボット視点の便利さは、案外人間の役に立たない
それではどのようなロボットが次のロボティクスになるのでしょうか?
たとえば、これだけテクノロジーが進んだ現在でも、結局私たちの身の回りにはロボットがいません。一般的には掃除機ロボットを導入している人がごく少数、ペットなどのパートナーロボットを所有している人がまれにいる程度です。一体、どうしてなのでしょうか?
この状態は、ロボット研究者としては悩みの種でもあります。ロボット研究者としては、自分が生み出したロボットを多くの人に使っていただきたいものなのです。しかし、実際は新しい技術を持つロボットは生み出されても、人間に使われないまま終わっていくのが現状です。
重要なことは、ロボットではなく、人間を見て考えるということなのかもしれません。つまり人間のそばにいる価値というものから逆算し、ロボットの機能を考えるということです。
たとえば、SFの世界では冒頭のシナリオのようなアシスタントロボットが出てきますが、人間は意外と自分のパーソナルなスペースに、大掛かりなロボットを入れたいと思わないのかもしれません。ベッドベイキングをしたり、掃除をしたり、水を用意してくれたり、おまけにベッドの近くで不気味に停止しているようなロボットであればなおさらではないでしょうか?
また、ハードウェアというのは、機能を実装するのが非常に困難です。スマートフォンに新しい機能を実装するためにはプログラムを実行するアプリを開発すれば良いだけですが、ロボットの場合はプログラムを実際の環境で実行するためのハードウェアをつくらなければなりません。汎用性を持たせ、多機能にするほどロボットは非常に複雑になります。複雑性が増すほど、故障する確率も高くなります。おまけに多機能のロボットは非常に高価なものとなり、さらに導入障壁が上がります。
また、「ぺらぺらしゃべるロボット」も、人間は導入したいとは思わないのかもしれません。冒頭のシナリオでロボットは人間に先回りしていろんなことを話してくれますが、これが長期に及ぶと、煩わしいと思うのではないでしょうか? 現代でも、スマートフォンのボイスアシスタントを例に考えてみれば分かりますが、スマートフォンが生活空間でずっとユーザーに話しかけ、それと話をし続けて快適な生活を送っている人を想像することは難しいものです。
このように、ロボットの概念自体を大きく捉え直さなければ、次のロボティクスというものは見えてこないのだと考えられます。案外、無口なロボットの方が現実的なのかもしれませんね。
使うときに現れて、使っていないときには消えるロボット
プロジェクト「サイバネティック・ビーイング」は、次のロボティクスを考え、新しい概念を試すことができる場と考えています。技能を融合したり、経験を共有できたりする、まったく新しい概念のロボットをつくっていくことが必要です。
そのためには、ただ盲目に高性能な人型ロボットをつくるということではなく、人間にとって一緒にいるときの快適さや、ときには人間の尊厳をきちんと守れているかといった側面にも発想を広げなければなりません。また、インタフェースとしては情動のようなものも再現していくような、新しさと柔軟性を備えたものを追求したいと思っています。
ひとつ仮説として現在進めているのが「ソフトロボティクス」のアプローチです。その名前の通り、柔らかい材料の形態と特徴を積極的にロボットの機能に応用していくアプローチをとる分野です。私はその中の「インフレータブルロボット」に関心を寄せています。
インフレータブルロボットは、端的に言えば、空気を入れて膨らませることで立体的なロボットになるものです。イメージとしては、少し前の作品ですが、ディズニーのアニメーション作品である『ベイマックス』(2014年)に登場するロボットです。流動性と軽さが、サイバネティックアバターの特徴にぴったりだと考えています。
まず、インフレータブルロボットは存在が流動的で、人間にとって快適な「オフ」の状態をつくることができます。空気を入れていないと、しぼんでぺったんこになってしまいますから、融合したり共有したりしない状態では、存在がほぼ無いものになります。誰も使っていないときに無言で停止しているロボットは、どうも人間の生活には馴染まないものですから、状態が流動的であるインフレータブルロボットは好適です。
また、基本的には膨らませる部分と、空気を送り込むファンからなるロボットですから、非常に軽量なロボットとして設計することが可能です。おまけに機能がシンプルで安価であることから、テレプレゼンスや、普及のしやすさにも有利です。
プロトタイプのものは固定的な外観のものですが、素材の選択によってテクスチャも付与できますし、持たせる機能や、置かれるシチュエーションによって人型や、人ではない型を選択することもできることから、外見と機能のカスタマイズのしやすさの面でも優れています。バーチャルアバターのように自由度の高いものにすることも可能でしょう。
サイバネティック・アバターはこれまでの人類が使ったことのないものですから、ロボットの開発も、従来の物理法則を覆すような発想が求められます。
少し奇抜な勘所が求められるものの、重要なことは、やはり人間の視点です。つまり操作する人が快適に感じるか、適応できるかが、設計においては大切です。さらには、実際の社会に出ていくロボットですから、通りを歩いている人が対面した時に、不快に思わないことなどもデザインに反映していかなければなりません。
まだまだ先は長いですが、実現すれば身体改変がリアルの世界でできるようになると考えられます。見たこともない概念をハードウェアとして実装していくことに、やりがいを感じながら研究を進めています。
(聞き手・文 森旭彦、聞き手 小原和也)



