
サイバネティック・アバターの新たな身体性を通して、人々が自身の能力を最大限に発揮し、多彩な技能や経験を共有できる未来社会像を議論するCybernetic being Meetupも第6回目の開催になります。
名古屋での開催となった第6回目は、イベントの冒頭に南澤孝太PMよりProject Cybernetic beingが目指す未来像についての紹介を行った後、感覚刺激を介して他者の感覚や意欲、経験を共有し、老化やフレイル(加齢に伴う虚弱)の予防に取り組む可能性の議論が展開しました。
ゲストとして、Projrct Cybernetic beingのプロジェクトメンバーである名古屋大学の平田さんと同プロジェクトメンバーである名古屋工業大学の湯川さんをお迎えしました。
身体のデジタル・トランスフォーメーションが拓く可能性
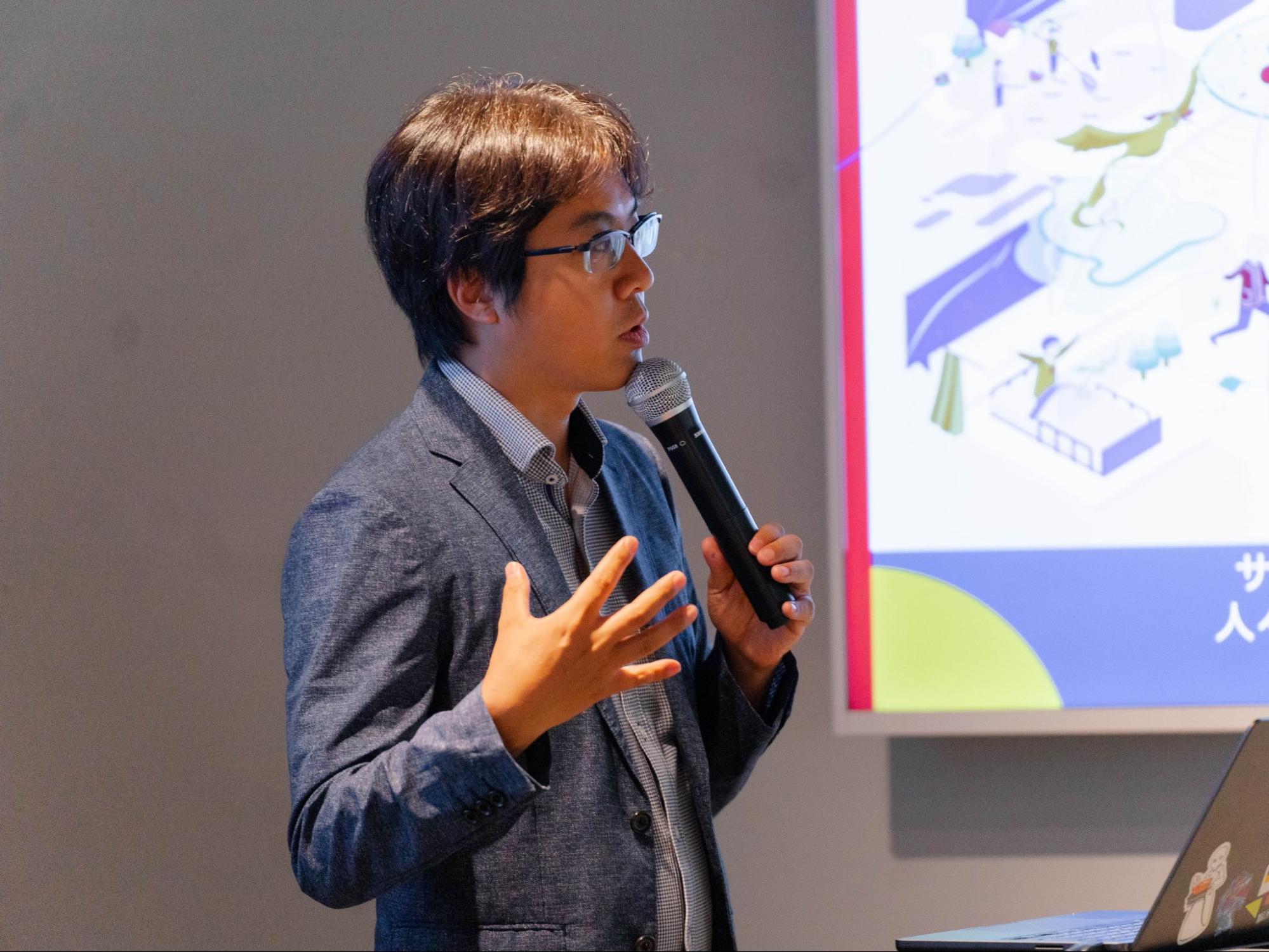
人々の働き方や暮らし方に大きな変化をもたらしつつあるAIとロボットの進化。特に「テレイグジスタンス(遠隔存在)」という概念は、ロボットを自身の分身として活用し、遠隔地での活動や体験を可能にします。
南澤PMは、この動きを「身体のデジタル・トランスフォーメーション」と表現し、これまでの情報(見る、聞く)だけでなく、感覚や経験、さらには身体で学ぶといった行為そのものをデジタル技術で実現する可能性を提示しました 。これにより、身体的制約を持つ人々(寝たきりの方、車椅子利用者、ALS患者など)が、アバターやメタバースを通じて社会参加し、仕事やコミュニケーションを行う新たな道が開かれています 。
「近い将来、人の感覚、経験、技、そして肉体や脳そのものがインターネットに繋がり、人々の間でこれらを自由にやり取りできる世界が訪れる。本イベントのテーマである『老い』に関しても、身体的な制約から解放される新しい生き方をテクノロジーがアシストし、健康寿命を延ばす可能性を秘めています。」(南澤)
認知的フレイルを乗り越える行為主体感とテクノロジー
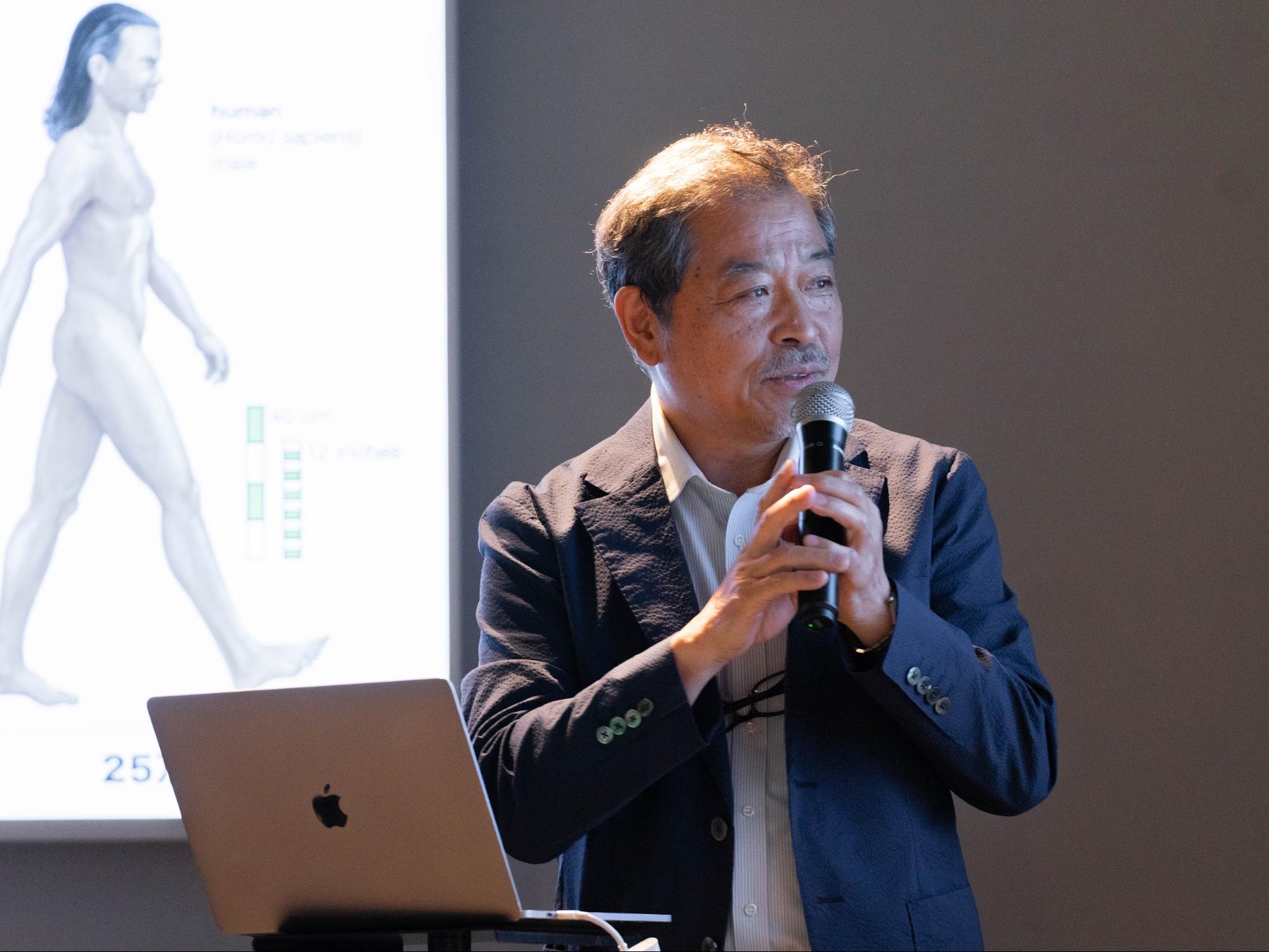
名古屋大学医学系研究科の平田仁さんは、整形外科医として、麻痺患者の運動再建を専門とする中で、脳の衰えにも着目して長年臨床経験を実践。
「『足腰が弱る』という人生の加齢曲線の、その背景に脳の衰えがあると我々は考えています。実際、認知症の前段階として“アパシー”──周囲への反応の鈍化が表れ、脳の広域ネットワークの機能低下が始まっていることが分かっています」(平田)
特に重要なのは、感覚情報を統合し、行動や感情を制御する脳の島皮質の働きです。この島皮質と、進化の過程で獲得された脳の各部位が連携する広範なネットワークを強化することで、一部の機能低下を補い、結果として身体機能も認知機能も維持できると平田さんは指摘します。
「脳のネットワークを効果的に強化するためには、『自分がやっている』という感覚(行為主体感)や 『やりたい』という意欲をいかに高めるかが極めて重要です。この主体的な感覚を刺激し、強化することが、脳のネットワーク活性化に直結し、また受動的な刺激だけでなく、自らが積極的に関与し、達成感を伴う体験が、脳の活性化と機能維持に不可欠なのです。」(平田)
その上で、高齢者の脳のネットワーク強化において、現代のテクノロジー、特にサイバネティック・アバター技術は、大きく寄与できると平田さんは強調します。
「サイバネティック・アバター技術は、『自分がやっている』、『やりたい』という感覚を効果的に引き出し、強化するための強力なツールとなり得ます。サイバネティック・アバターを通じて『他者の経験を伝達してもらい、自分で学習し、自分でできるようになった』という主体的な経験を促すことで、その効果は飛躍的に高まると考えています。」(平田)
「補助輪」から始まる、軽やかな挑戦

名古屋工業大学の湯川光さんは、感覚刺激、特に触覚や嗅覚の共有技術を専門としています。人と人の感じ方や考え方の違いに興味を持ち、他者の感覚を共有することで相互理解を促す研究に取り組んできました。 今回のプロジェクトでは、「老い」を新たなテーマに据え、高齢者の認知機能や身体機能の衰えに対し、サイバネティックアバター技術でどのように挑戦をサポートできるかを探っています。
「高齢者支援において、平田先生の仰るように自分にとって少し負荷のあることでも、自発的に取り組んでやりがいを感じる内的報酬が重要です。それを生みだすにはより積極的で、かつ低認知負荷な運動サポート技術と行為主体感を維持し、さらに増強できるようなシステムが必要があると考えました。行為主体感というのは、『自分がその行動をした』と心から思える感覚のことです。」(湯川)
ドラム演奏を対象とした検証では、高齢者の認知負荷を低減しつつ主体感を損なわないよう、「異なる感覚刺激の組み合わせ」に注目した動作教示システムを開発しました。具体的には、一定のリズムを刻む右手には時間的な分解能に優れ、ズレを強調しやすい触覚刺激(手首の振動)を、そして左手には空間的提示が可能で予測を促す視覚刺激(LEDの光)を採用。認知神経科学の知見に基づき、異なる感覚刺激の方が干渉が少なく認識しやすいという特性を活用しました。
「このシステムは、感覚刺激を用いることでユーザーが手本とのずれを直感的に感じ取り、自発的に動作を調整できるよう設計されており、強制的な身体駆動による「操り人形」のような感覚を避けることを重視しています。」(湯川)
開発したシステムは、同種の感覚刺激を用いるよりも手本とのずれが小さくなる傾向が確認されました。また、子どもが教師役、保護者が学習者役となるドラムセッションイベントでもその有効性が示され、簡単なレクチャーと練習で高いパフォーマンスが達成されました。
「このシステムは、『自転車の補助輪』のようなものだと考えています。補助輪があるからこそ、最初は不安でも新たな挑戦へ踏み出せるように、高齢者の方々が『あ、自分にもドラムが叩けるんだ!』とか『じゃあ、こんなことにも挑戦できるんじゃないか?』と、軽やかに挑戦できることを応援したいと考えています。そして、『老い』による衰えだけでなく、誰もが持っている『苦手』を克服して、どんなことにも軽やかに挑戦できる社会の実現を目指していきたいと考えています。」(湯川)
「高齢者の変化」から「社会実装」へ

クロストークでは、南澤PMがモデレーターを務め、平田さん・湯川さんとともに「高齢者の変化をどう捉えるか」という問いから対話が始まりました。
「高齢者が変わる瞬間とは、“やりたいこと”を見つけたときです。新しい技術に触れて『意外にできるかも』と思えることで、身体も脳も動き出す。これは、子供の頃のような『わくわく感』が、記憶の定着や新たな行動に深く関わっているからだと考えています。」(平田)
湯川さんもまた、学習への動機づけにおいて「わかる/できる」の手応えが重要であるとし、補助的な刺激によって「自分にもできた」という体験が自信につながると述べました。
会場からは、「高齢者の認知機能低下に対して、感覚刺激をどう最適化しているか」という質問が寄せられました。
「視覚、聴覚、触覚といった異なる感覚は、実は別々の情報としてではなく、記憶を統合するための『丸めた形』で処理されます。加齢で衰える特定の感覚を、他の感覚で『補完』したり、記憶で『保管』したりすることで、全体的な認知負荷を軽減することができます。」(平田)
「私たちのドラムシステムでは、視覚と触覚という異なる情報を提供することで、ユーザーに『選択肢』を与え、ご自身で集中する情報を切り替えることができるようにしています。情報が多いと混乱を招く恐れがありましたが、これが、むしろ認知負荷を下げている可能性があります。」(湯川)

さらに議論は、感覚や身体の支援にとどまらず、「心」への働きかけへと広がります。
「システムと一人で向き合うだけでなく、インストラクターや他の参加者との関わりが、モチベーション向上に不可欠であると強く感じています。」(湯川)
「コロナ禍での経験から、都市部では深刻な『高齢者うつ』の問題が見えました。私たちのドラムプロジェクトへの参加が高齢者うつのスコアを改善させた事例もあり、コミュニティとの交流や目標を持つことが心の健康に繋がる可能性を示唆しています。」(平田)
最後に南澤PMは、今後の社会実装に向けた課題として、制度設計や評価軸の転換に言及しました。
「今までは『自分が社会に参加できる』とか『働く』ということと、『肉体が介護を必要とする』ということは同一であり、肉体的に介護されながらでないと移動もできないし、働けない、というのが常識でした。しかし今、肉体的な介護が必要なままでも、実質的に動けるという状態が起きている。 この状況で、日本の社会として、どこまでを『肉体のカバー』という話にするのか。そして、その方の内面や能力的な部分、さらにはデジタル越しに発揮できる能力というものをどう評価し、どこに境界線を引いていくのか、という社会制度的な課題の議論が必要だと考えています。
これは非常に今、岐路にある問題であり、このような制度的課題も含めて、我々も取り組んでいきたいと思っている。もちろん時間はかかるが、まずは具体的な事例をしっかり示していくこと。そして、その事例が本当に『役に立つ、良いことだ』と社会に認知されることから、徐々にそういった新しい制度が作られていく形になると考えています。」(南澤)
それぞれの登壇者が、技術、脳科学、感覚設計の観点から「老い」を捉えた今回のMeetup。クロストークでは、その実践的な接点が見出され、今後の研究と社会実装の方向性を照らす時間となりました。
当日のイベント内容を詳しく知りたい方は、下記のYouTubeのアーカイブから、当日の配信の様子をご覧いただけます。



